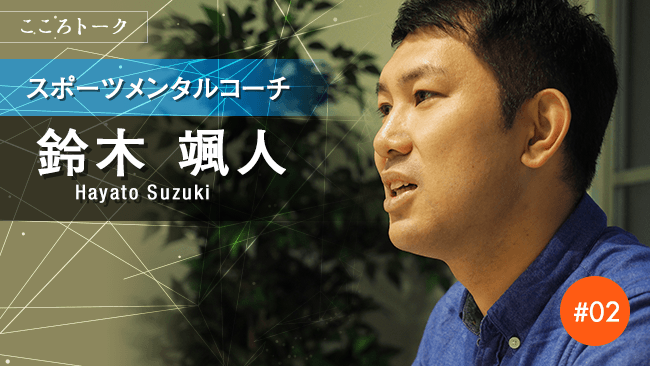森の中へ入って五感を解放する。それがイノベーションにつながる。一般社団法人 森と未来 代表 小野なぎささん 前篇

今回の「こころトーク」は、森と未来代表の小野なぎささん。大学で林学を専攻した後、まだ森の癒し効果など注目を浴びていなかった頃、森と健康分野のエキスパートとしての道を選びます。癒し、健康ブーム、さらにAI時代を迎え、現在、企業向けプログラムでは森の力を借りながら「次世代リーダーの感性を育てる」ことに注力し、さらに社名Future with Forestにあるように、森と一緒に未来を考える活動を行います。国土の約7割を森林が占める日本に暮らす私たちにとって、実はとても身近な森や自然に関するお話をうかがいました。前篇・後篇2回に渡ってお届けします。
うつ病3万人時代に、森で健康になる研修からスタート
編集部:森に関連するさまざまな活動をされていますが、そもそもなぜ森を健康と結びつけて活動をしようと思われたのですか?
小野:私は東京生まれの東京育ちなのですが、両親がとても自然が好きで、小さい頃から毎週末のようにキャンプへ行って、「自然の中へ行くのは楽しいな~」「森は気持ちがいいな~」ということを肌で感じながら育ちました。
森好きが高じて大学では林学を専攻しましたが、専門的に勉強してみると日本の森林・林業をとりまく話題は明るい話が少なくて。元々健康に関心があったこともあり、次第に「もっと森で健康になれる方法はないのかな?」と思うようになりました。
すると、大学3年生のころ、国から「森林の癒し効果」などのエビデンスが出てきて、その癒し効果が心の健康につながるということも徐々にわかってきました。
時代は、うつ病が3万人を突破して、働く人のストレスが次第に問題になりはじめ、ようやく人事がメンタルヘルス対策にとりかかった頃でした。私は働く人へ向けた心の健康対策を行っている会社に就職し、産業カウンセラーの資格などもとって、まずは企業向けの研修を森の中でやってみました。
人事担当者や保健師さん向けの勉強会を森でやってみると、研修が終わる頃にはとても表情がやわらかく会話も自然になるのを目の当たりにして、「都会で働く人は、自然の中に来ることが大事なのだな」と実感しました。
人間力や人間ならではの感性がイノベーションには必要
編集部:現在は、どのようなテーマで研修されているのですか?
小野:今は、主に「感性を育てる」ことをテーマに森で企業研修を企画しています。会社は社員により生産性の高い仕事をしてほしいし、利益を生み出すための学びにはお金をかけますから、ある時からマイナスをゼロにする取り組みではなく、よりプラスになる働きかけをしてみようと考えました。
具体的には、「次世代リーダー」や「管理職」「役員職」を対象としたプログラムで、頭で考えるのではなく、身体感覚を使う時間を積極的に取り入れています。
多くの企業が、AIの進展に伴って会社の中で変革が求められています。企業としても、これからのリーダーたちには、自分たちでイノベ―ティブなことを生み出してほしいというニーズが強くなっていると感じます。
そして、イノベ―ティブな発想のためには、まずは頭で考えるのではなく、身体感覚がしなやかに反応できるよう準備することが必要なのです。ですから、都会の中で使うことが少なくなってしまった感覚を取り戻すことに森の力を借りています。

森の中で、まずは「五感」を意識する
編集部:必ず森の中で行うことはありますか?
小野:森の中は屋内の研修施設と違って環境がいつも同じというわけではないので、必ず毎回同じプログラムを行うことはできません。でも、意識して大切にしている点が二つあります。1つは「五感を意識する」こと。そして2つめは「森の多様性と循環に触れる」ということです。
編集部:まずは五感ですね。
小野:わたしたちは普段の生活で視覚ばかり使っています。何かを判断するときにも、まずは見た情報、それに聞いた情報を加えたりして判断することを繰り返しています。それが悪いわけではありませんが、人間はAIには持つことができない身体を持っています。身体はたくさんのセンサーがあるので、見えない情報もキャッチすることができます。
実際に、森の中で目を閉じると、視覚以外の感覚がぐっと開きます。遠くの音、動いている音、肌に触れる風や木や土の匂いなど。都会でアロマなどの香りを嗅ぐと、嗅覚のみを積極的に使うことになりますが、森の中へ入ると五感全てに刺激が飛び込んできます。五つの感覚以外にも、何かの気配や直感のようなものも含めてセンサーが働き出します。
昔感じたワクワク感など、オーセンティックな自分の感情に触れることが大切
編集部:参加者の方はどのような反応を示されますか?
小野:みなさん「懐かしい」と仰いますね。「昔の実家を思い出した」とか、「子どもの頃の記憶が蘇った」とか。
森へ行くことで、仕事をしている今の自分ではなくて、自分の過去の記憶につながることができます。
さらに、「思い出した記憶の中で、どんな感じがしましたか?」と聞くと、「すごく楽しかった」「ワクワクしていた」と仰います。そして、「今は会社で色々縛られているものもあって、ワクワクしてないな...」と気づかれるのです。
私は、このいろいろなルールに縛られていることが、イノベ―ティブなことが起こらない1つの原因だと思っています。自分の感覚を使い、そのとき感じた感情が繋がると、その人の感性が見えてきます。人はそれぞれ生まれ育った環境や、学んだこと、見たもの、聞いたもの、食べたもの、全て異なるので、感性はその人の個性なのです。
積極的に五感を使って、どんな感情が沸き出てくるかを丁寧に確認し、本来の自分、オーセンティックな自分に触れてみると、新しい気づきを得ることができます。

森の研修を終えて、「人と違っていいんだ」と思えるようになる
編集部:懐かしいというのは、ある程度自然に触れて育って原体験がある人の感覚だと思うのですが、原体験がない人でも同じですか?
小野:確かに、原体験の有無によって反応は違います。コンクリートの建物の中で生まれ育ったような人たちや若い世代にとっては、森はアミューズメントパーク状態です。ジブリの世界のようなもので、全てが初めて見るモノ、初めて知る感じで、それはそれですごく新しい刺激になっていることがわかります。
ただ、原体験や世代にかかわらず共通するのは「なんか気持ちがいい」「なんか安らぐ」「なんかいいよね~」という感覚です。
編集部:企業やチームでは何が変わるのでしょう?
小野:例えば、森の中で各自気になるものを集めてきて、最後になぜそれを集めたのかをチームでシェアするワークがあります。これは、その人のモノの見方や価値観がみえてきます。歩く道の選び方も個性ですし、ある木の実を「気持ち悪い」という人もいれば「私には輝いて見えた!」という人もいます。そして、「どうして?」と聞いていくと「昔から暗闇の中でもなんか輝くものが好きで、自分はずっと輝くことに憧れがあったのだと思います」と言ったことが再発見され、その人を知ることにもつながります。
こうした研修を体験した後、ある人事の方は「森で過ごした時間のあと、チームの会話の質が変わりました」と言われました。「人と違っていい」ということが出せるようになり、「個性の違いを認め合うことができるようになった」と喜んでおられました。
森の多様性を自分のいる社会に置きかえて考えてみる
編集部:では、もう1つの視点「多様性と循環」についても教えて下さい。
小野:多様性と循環というのは、視野を広げるということにも近いです。
近年、企業でもダイバーシティを掲げていますが、多様なものの集まりではなく、多様な性質をもつ人たちがあつまって同じ目標に向かっているというのが会社です。
森の中には、いろいろな生命が一緒に生きています。そして、循環しながら何百年も成長を続けています。鳥は木の実を食べ、糞を落とすことで木の種子を広げ、落ち葉は土壌の微生物が分解して木々の栄養となります。森の生き物は、必ず誰かが誰かを支え全てがつながっています。森の木々が太陽に向かって元気に伸びていけるのは、見えない土壌の中でしっかりと根っこ張っているからです。
見える世界だけでなく、見えない所で強い根を張り繋がっているから森という共同体が成り立っている、という森の生態系と、見えない所で人と人がつながり、支え合っているから会社という組織や社会が成り立っている、という仕組みを照らし合わせて話してみると、受講者の中からは「わたしは根っこの役割ですね、見えないところでみんながうまく働けるようにサポートしたい」といった声が挙がったりします。
編集部:お話を伺っていると、森と日本人は相性がいいのだな、と思いました。さらなる森の魅力や可能性について、次回もお話を聞かせて下さい。
後篇に続く
小野なぎさ(おのなぎさ)NAGISA ONO
一般社団法人森と未来 代表理事
東京都調布市出身。東京農業大学 森林総合科学科卒業後、企業のメンタルヘルス対策を支援する会社へ就職し、認定産業カウンセラー、森林セラピストの資格を取得。約10年間で、森林を活用した研修プログラムの開発、健康リゾートホテル事業、海外のメンタルヘルス事業の立ち上げを経験。山村地域と連携し森林浴を活用した観光プラン、企業研修、人材育成を実施し、執筆や講演活動を行う。2015年一般社団法人 森と未来を設立し現職。2019年より林政審議会委員に就任。著書に『あたらしい森林浴』(学芸出版社、2019.7.20発売)
編集:COCOLOLO ライフ magazine 編集部